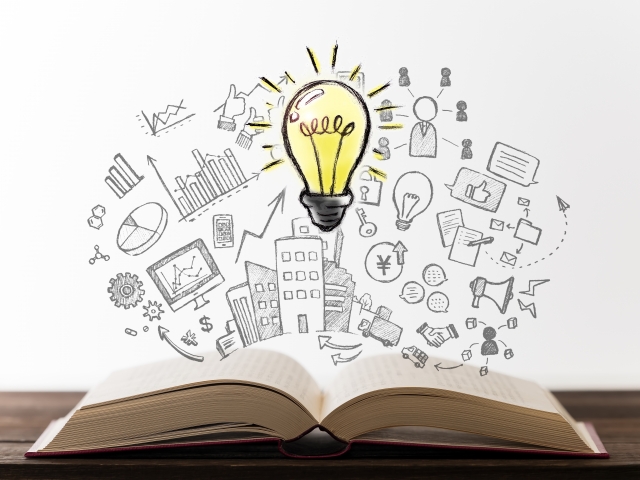小論文指導で有名な樋口裕一先生の著書です。
読解力を鍛えることにより頭をよくしていこうという本です。
具体的には
1、語彙力を鍛える
2、文章力を鍛える
3、読解力を鍛える
という3ステップを演習を通じて読解力をつけていきます。
本を読んでいく中で正直、自分の文章がいかにダメかを思い知らされました。
この本を買ってよかったです。何回も読んで頭を鍛えています。
- 語彙力を鍛える
- 問題1 敬体を常体に、常体を敬体に改めてください
- 問題2 ( )を埋めて、具体例を示してください
- 問題3 ( )内に、それ以前の部分をまとめるような言葉を入れてください
- 問題4 次の二つの文を一つにしてください。また、一つの文を二つ以上にしてください
- 問題5 次の文を、漢字熟語などを加えて簡潔な文に改めてください。
- 問題6 次の文は持って回った表現が多く、誰にでもわかりやすい文とは言えません。もっとわかりやすい
- 問題7 次の表現は直接的過ぎてぶしつけです。もっと婉曲的な表現に改めてください。
- 問題8 次の分を「である」「だ」「です」を用いないで言い換えてください。
- 問題9 次の文を( )に漢字熟語を入れて言い換えてください。
- 問題10 次の文には誤りが含まれます。正しく改めてください。
- 文章力を鍛える
- 読解力を鍛える
- まとめ
語彙力を鍛える
まず取り組むべきなのは、語彙力を養うことです。
といっても故事成語やことわざを覚えることでなく、言葉をつかえるようにすることです。
そのためには言い換え力を鍛えます。
一つの言い方ではない、もっと別の表現があることを知り、様々な表現を自分のものにすることによって語彙力、読解力がついてきます。
これを別の表現で言うとどうなるということを考えてきます。
どのような演習があるのかは以下の通りです。
問題1 敬体を常体に、常体を敬体に改めてください
情けないことですが、常体と敬体をあまり意識したことはありませんでした。
常体と敬体は日本語の文章の基本です。
常体と敬体をごっちゃにした文章を書かないということに気を付けてきます。
終止形+ですを使わない方がいい。
楽しいのです。
ではなく楽しいのです。楽しく感じられます。のようにしましょう。
問題2 ( )を埋めて、具体例を示してください
文章を読むときも書くときも、具体と抽象の間を行き来している。
具体的なことが書いていなくても常に具体的な内容を意識しておかなくてはなりません。
問題3 ( )内に、それ以前の部分をまとめるような言葉を入れてください
文章を書くとき、読むときは、具体化とともに抽象化も大事です。文章で示された内容を一言で抽象的にまとめる練習をします。
問題4 次の二つの文を一つにしてください。また、一つの文を二つ以上にしてください
文章を簡潔にまとめたりする練習になります。また文章を短く切る習慣をつけておく方がよいです。
問題5 次の文を、漢字熟語などを加えて簡潔な文に改めてください。
話し言葉の平易な文を、新聞などで用いられる簡潔な文に改める練習です。
日常的な砕けた表現と簡潔な文体の両方を使いこなせるようにしておくことが重要です。
この演習は意外と難しかったです。
書き換えた後全く雰囲気が変わるのが恐ろしいです。
問題6 次の文は持って回った表現が多く、誰にでもわかりやすい文とは言えません。もっとわかりやすい
問題5とは逆に難しめの文をわかりやすい文に改めるのも重要です。
難解な文を自分の頭の中でわかりやすい文に改められるということは文を理解できているということになりますね。
問題7 次の表現は直接的過ぎてぶしつけです。もっと婉曲的な表現に改めてください。
思っていてもそのまま口に出せないことがある。とりわけその表現が人にとって失礼にあたるとき、それを口に出すことはできない。そのような場合の表現を工夫することも、大事な語彙力の表現の訓練につながります。
「あなた」という人称代名詞はしばしば失礼にあたるので使わない方がよいです。
敬語を使ったり、遠回しの表現を使うのがよいです。
あまり~ではない
私には~に思える
等を使う。
それと断定しない。
問題8 次の分を「である」「だ」「です」を用いないで言い換えてください。
「である」「だ」「です」ばかりの文章だと硬くてぎこちない文体になってしまいます。文末の言い回しをほかの表現に変えることで、リズムを変えることができ、文体に変化をつけることができます。
~にほかならない
~として~
といえる
といえるだろう
等を使えると文章が楽になります。
問題9 次の文を( )に漢字熟語を入れて言い換えてください。
言い換えの語彙を持っていると自由に字数の調整もでき、簡単な文体、わかりやすい文体など自在に文章を演出することが可能です。
~性、~化などの言葉を知っていると便利です。
問題10 次の文には誤りが含まれます。正しく改めてください。
「れる」「られる」の使い分けに注意してください。
命令形が「~ろ」で終わる動詞は「られる」投げろ⇒投げられる
命令形が「~れ」で終わる動詞は「れる」走れ⇒走れる
文章力を鍛える
読解力をつけるには文章を書く練習をしましょう。
どのような文章かというと小論文です。
小論文を書くことによって、論理的な文章力がつき、自分なりの考え方をまとめるのにも役立ちます。それではどのように小論文を書くのか見ていきます。
小論文の書き方1
小論文とは一つのイエス・ノーを判断する文章です。
その根拠を示し、読んでいく人に納得がいくように説明するのが小論文です。
小論文の書き方2
小論文には型が3つあります。
基本A型
基本B型
基本C型
基本C型は4部構成になり、
第一部 問題提起
第二部 意見提示
第三部 展開
第四部 結論
小論文の書き方3
3WHAT3W1Hに沿ってアイデアメモを作成します。
3WHAT3W1Hとは
(3WHAT)
それは何か(定義)
何が起こっているか(現象)
何がその結果起こるか(結果)
WHY(理由、根拠)
(3W)
WHEN(いつからそうなのか、それ以前はどうだったか=歴史的状況)
WHERE(どこでそうなのか、他の場所ではどうなのか=地理的状況)
(1H)
HOW(どうやればいいか=対策)
小論文の書き方4
メモを見ながら構成します。
基本C型で書くならば自分の主張の根拠を明確にして第3部に置きましょう。
小論文の書き方5
書くときの注意点です。
「だ・である調」(常体)を用いる
一文を長くしない
書き言葉を用いる
抽象と具体を織り交ぜる
言葉の定義を明確にする
自分のことを「自分」「俺」と書かない
読点の打ち方にはルールがある。
小論文の書き方6
各部分の書き方です。
第一部 問題提起
書き出しを客観的事実で始めるのが良いです。
第二部 意見提示
確かに~
反対意見(十分に書く)
しかし(短くまとめる)
第三部 展開
自分の主張の根拠を書く
第四部 結論
余計なことを書かずにイエスかノーをまとめます。
小論文の書き方7
短い字数で根拠を示すのは難しいが、三段論法を使うと説得力が増します。
そもそも三段論法
説得力を持たせるため「そもそも三段論法」を使います。「そもそも三段論法」を第三部に書き、説明を加えるとすっきりまとまった小論文になります。
1.最初に理想的なあり方を考える(読者が一般論として納得できるように示す)
2.1と比較して理想に近いかを考える。
3.理想に近ければよいとみなし、外れていればよくないと判断する。
その結果三段論法
こんなことが起こると、必然的にこうなる。その結果こんなことが起こる。だから、これはよいことだ
と判断する論法です。
リアリティを持たせる
リアリティを持たせるのは重要なので簡単な方法を説明します。
●具体的に示す
●描写する
●動きを出す
●色彩や音響を加える
●ほかの人では気づかないディテールを示す
●きれいごとを書かない
●重ね言葉・形容句を用いる
読解力を鍛える
ついに最後の読解力です。
読み取りの手順1
抽象と具体を解きほぐす。
抽象と具体を意識しながら読んでみましょう。
読み取りの手順2
確かに・・・。しかし・・・。のパターンをつかむ。
読み取りの手順3
四部構成の型で読む。
読み取りの手順4
キーワードとその意味を正確にとらえる。
ほとんどの場合、最も出てくる用語がキーワードです。そこに特殊な意味合いが込められている場合があるので注意しましょう。
読み取りの手順5
何に反対しているかを考える。
読み取りの手順6
主張を把握し、根拠を整理する。
読み取りの手順7
要約してみる。
もし余裕があれば、100字程度で課題文を要約してみましょう。
主要な主張は何か、そのためにどのような説明がなされているかをまとめましょう。
読み取りの手順8
3WHAT3W1Hで文章中に語られていることを検証しましょう。
まとめ
以上長々と引用してしまいましたが、非常にいい本だと思いました。
この本はまとめを読んだだけではだめなので、本を購入して演習をすることをお勧めいたします。